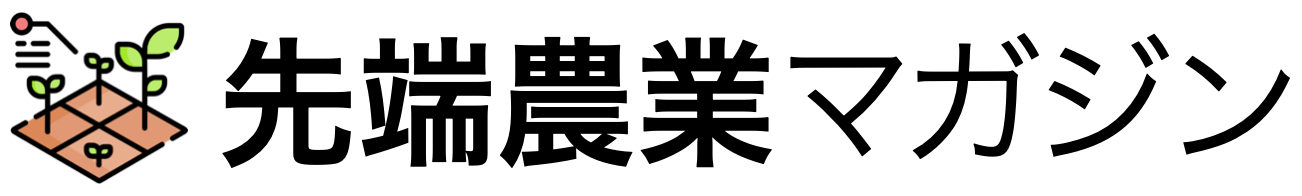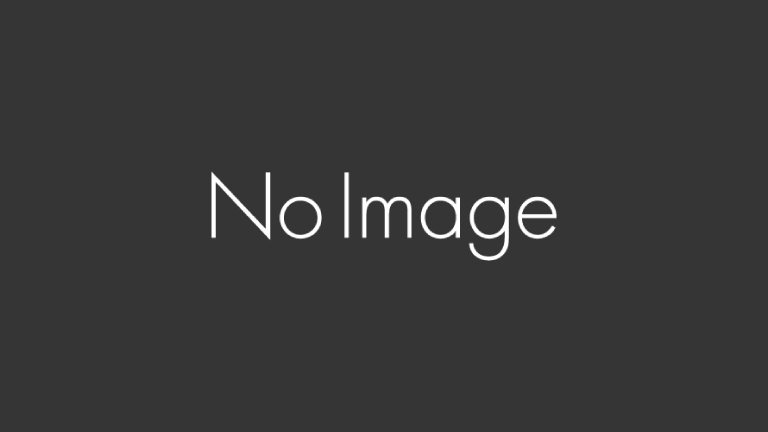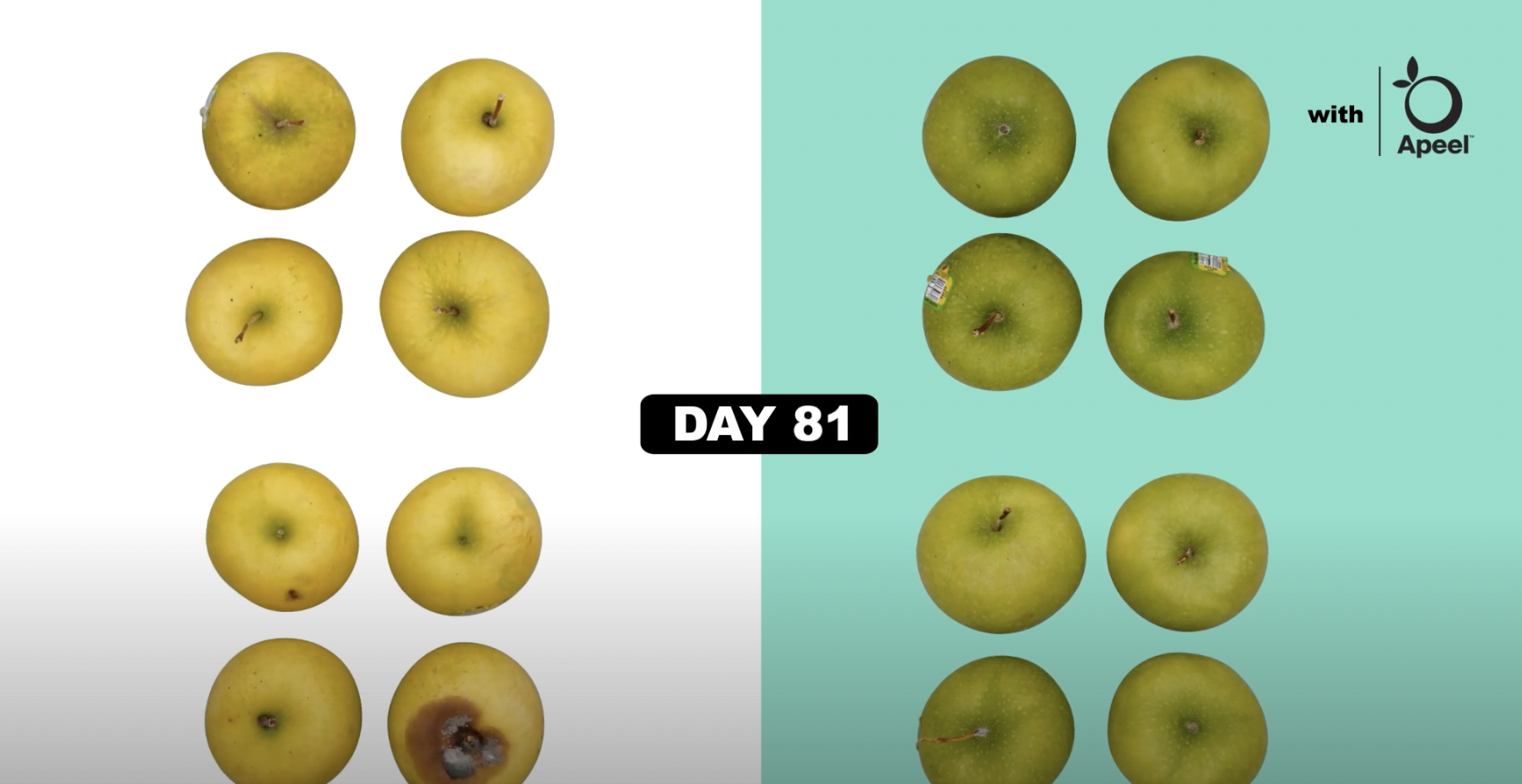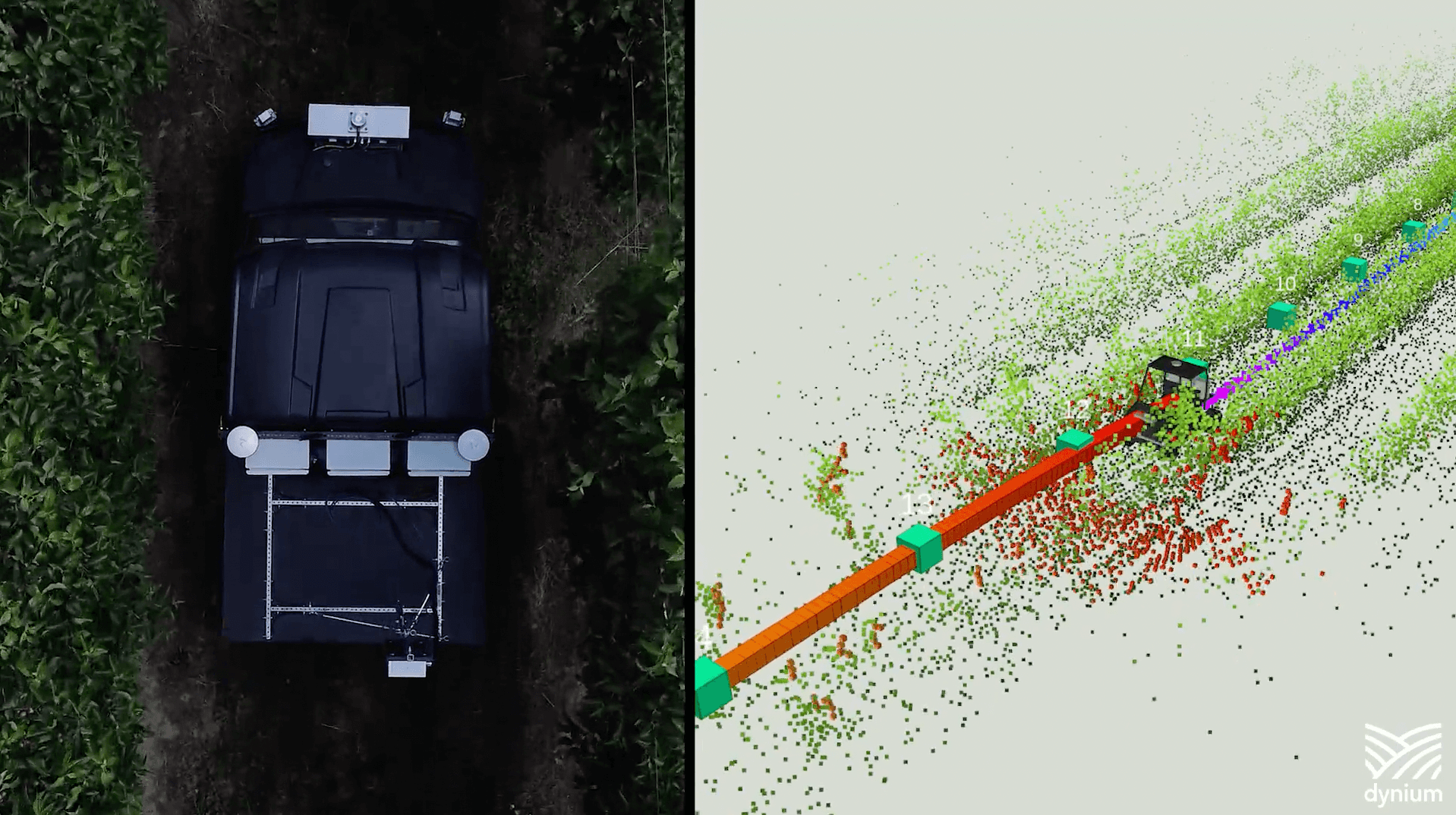温室内の除湿に加え、温度調整と空気循環が可能な除湿機を開発・販売するDryGair社について解説
事業概要 DryGair社は、2010年に設立された、温室内の湿度制御ソリューションとして除湿機の設計と開発を行うイスラエルの農業テクノロジー企業です。従業員数は1〜10名と推定されています。 最も効率的な冷媒ベースの機械と、独自の空気循環に基づいたDryGair社の除湿機は、エネルギー効率の高い方法で、温室内の理想的な気候条件を維持します。 Youtube動画:https://youtu.be/ […]