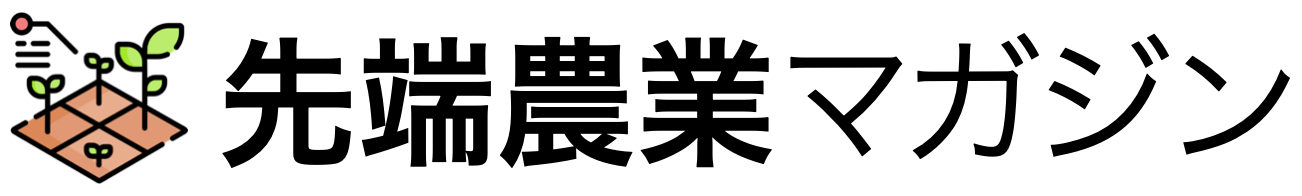近年、「ファインバブル」という技術がさまざまな分野で注目されています。農業の現場でも、このファインバブルを活用した装置が登場し、作物の生育促進や品質向上に役立つと期待されています。では、農業用ファインバブル装置とは一体どんなものなのでしょうか?ここではファインバブル技術の概要と歴史、農業における効果の理由(科学的根拠)、国内外の導入事例、そして代表的な製品やメーカーについて、農家の皆さんにもわかりやすい語り口で紹介します。
ファインバブル技術の概要
ファインバブルとは:非常に小さな気泡(泡)の総称です。普段目にするお風呂の泡や炭酸水の泡よりずっと小さく、直径が100マイクロメートル(0.1mm)未満の泡を指します1。さらに大きさによって2種類に分類され、直径1µm(マイクロメートル、0.001mm)以上100µm未満のものを「マイクロバブル」、1µm未満の極めて小さいものを「ウルトラファインバブル」と呼びます1。要するに、ファインバブルとは“目に見えないほど小さな泡”なのです。
こうした超微細な泡には、普通の泡と異なる特性があります。水中ではゆっくり浮上したり、ごく小さいものは水中に長期間安定して存在することもできます。また、泡が小さいほど内部の圧力(自己加圧効果)が高まり、泡の中の気体を周囲の液体に溶け込ませやすいという性質もあります2。さらに特筆すべきは、ファインバブル表面が**マイナスの電気(負電荷)**を帯びる点です。このためファインバブル同士は反発し合い、一つ一つが長く安定して水中に存在できます2。また負電荷を持つことで、周囲のプラスに帯電した物質(例:養分のイオン)を引き寄せる作用も持っています。このような独特の性質を活かして、ファインバブルは様々な分野で応用が進んでいます。
国際標準化:ファインバブルという用語や定義は、日本発の技術でありつつも現在では国際標準化機構(ISO)で正式に定義されています1。2012年に日本でファインバブル産業会(FBIA)が設立され、産学官連携で標準化や技術開発が進められました。その結果、2017年にISO規格として「直径100µm未満の気泡をファインバブルとする」定義が策定され、細かな分類や測定手法も国際標準となりました。日本ではかつて「ナノバブル」など様々な呼称も使われていましたが、現在はISOに準拠して**ファインバブル(マイクロバブル・ウルトラファインバブル)**という用語に統一されつつあります1。
ファインバブル技術の歴史
古くからの泡研究:実は、泡そのものの研究は古く紀元前から行われてきました(アルキメデスの浮力発見など)2。しかし、産業応用としての超微細な泡の研究が本格化したのは主に1990年代以降です。日本において、1990年代後半から2000年代初頭にかけて「マイクロバブル」「ナノバブル」という言葉が登場し、超微細気泡の不思議な効果が注目され始めました2。
日本発のイノベーション:ファインバブル技術は日本で生まれ、世界をリードしてきた分野です。例えば約20年前の2000年頃、日本の研究においてカキ(牡蠣)の養殖にマイクロバブル水を使ったところ成長が促進されたことが確認され、この時に「マイクロバブル」という用語が使われ始めたと言われます*2。その後、この技術は魚の養殖や農業などにも応用が広がり、各方面から注目されるようになりました。
2012年には前述のファインバブル産業会(FBIA)が発足し、日本主導で本格的な標準化と産業化の動きが始まります。国内の産学官が協力し、世界初の学会発表でファインバブルの洗浄・殺菌効果を証明したり、ウルトラファインバブルの存在自体を証明する研究報告が相次ぎました。そうした取り組みを通じ、ファインバブル技術は**「日本発の革新的技術」**として地位を固め、現在ではシャワーヘッドや浴槽、水処理装置から農業用機器に至るまで、様々なファインバブル製品が実用化されています。市場規模も拡大傾向にあり、日本国内はもちろん世界的にも今後ますます成長が期待されています。
なぜ農業に効果があるのか? ~ファインバブルの作用と根拠~
超微細な泡が農業に良い影響を与えると言われるのは、主に次のような科学的な根拠・メカニズムが考えられているためです。
- 水中の酸素量を増やす:ファインバブルを水中に発生させると、水への酸素の溶け込み量(溶存酸素量)が増加します。小さな泡は表面積が大きく、ゆっくり溶けて消えるため、水に酸素を効率よく供給できるのです。植物の根は酸素を必要とするので、酸素豊富なファインバブル水で灌水することで根域の酸欠状態を防ぎ、根が健全に育ちます。その結果、根から作物全体に送られる**成長ホルモン(サイトカイニン等)**の合成も盛んになり、生長促進につながります*3。
- 養分の吸収を助ける:前述したようにファインバブルの表面は負に帯電しており、肥料中の窒素やミネラル分などプラスの電荷を持つ養分イオンを引き寄せる性質があります。ファインバブル水中では養分が泡にくっつきやすくなり、その泡が根に集まることで養水分の吸収効率が上がると考えられています*3。また、微細な泡が土壌や培地の隙間にまで浸透しやすいため、水や肥料が根圏によく行き渡る効果も期待できます。
- 有用微生物の活性化・病害抑制:土壌中には植物の生育を助ける好気性の微生物(微生物肥料など)が存在しますが、根の周りが酸欠だとそれらが十分に働けません。ファインバブル水で土壌に酸素を届けることで、土中の好気性菌の活動が活発化し、例えば窒素分を長く保持して供給してくれるなど土壌環境が改善します*3。さらに根腐れの原因となる嫌気性の菌や病原菌の繁殖を抑える効果も報告されています。結果として病気に強くなる、根腐れが起きにくい健全な作物生育が促されます。
これらのメカニズムによって、ファインバブルを使うと「水と空気だけ」で作物の生育を後押しできる可能性があるわけです*3。実際、学術研究の場でも検証が進んでおり、例えば滋賀県立大学の研究ではマイクロバブル水の電気的性質(ゼータ電位)が水耕栽培のコマツナ(小松菜)の生育に良い影響を与えることが示唆されています。また、福島大学と東京大学のグループによる報告では、ウルトラファインバブル水を用いた作物栽培で成長促進や収量増加の要因を調べる研究成果が発表されています(第6回ファインバブル学会連合シンポジウム, 2020年)など、科学的エビデンスの蓄積が進んでいます。
さらに現場の声として、「水温が高い夏場でも根元まで酸素が行き渡るので根腐れが無くなった」「養液栽培で培養液が腐敗しにくい」といった報告もあります。ファインバブル水の導入によって根張りが理想的になる(根量が増える)ことや、肥料の効きが良くなることを体感する農家も増えてきています。もちろん作物や環境によって効果の現れ方は異なり、万能の魔法ではありませんが、こうした科学的原理に裏付けられたメリットが期待できるため、多くの生産現場で試されているのです。
国内の導入事例
日本国内では、ファインバブル技術を農業に活用したさまざまな実証や導入事例が報告されています。経済産業省九州経済産業局が2018年にまとめた事例集*5によると、例えば次のような成果が確認されています。
- いちご(高設養液栽培):酸素ファインバブル水を用いたところ、総収穫量が24%増加し、果実の糖度も0.9度向上しました*5。高品質ないちごを多く収穫できる結果となっています。
- ミニトマト(水耕栽培):ウルトラファインバブル水で栽培したところ、収穫量が約20%増加し、糖度も約2度上昇しました*5。収量アップだけでなく甘みも増すという好結果です。
- レタス(植物工場・水耕栽培):酸素ファインバブル水を使った栽培試験では、収穫時のレタスの重量が約2.5倍(播種から50日後の比較)に向上しました*5。大幅な増収効果が報告されています。
- 稲作(育苗):水稲の苗づくりにファインバブル水を散布すると、根の長さが通常より2倍以上に発達した例があります。また、苗の欠株(育苗中の苗枯れ)が無くなるといった成果報告もあります。しっかり根張りした丈夫な苗が育つことで、その後の生育も安定するメリットが期待できます。
これら以外にも、「ホウレンソウで硝酸態窒素濃度が低下し品質向上」「大麦の発芽率が向上」「観葉植物の挿し木発根率が改善」など、多種多様な作物でファインバブル導入の効果が報告されています5。付随的な効果として、根腐れが発生しなくなったことや培養液中のバクテリア繁殖が抑えられた例もあり、特に植物工場や温室栽培など高度に環境制御された場面、あるいは高付加価値作物の生産において大きなメリットが見込まれるとされています5。
また、実際に導入した農家からは「今までより成長が早く収穫期間が短縮できた」「夏場の根の傷みが減り、後半の収量落ち込みが少ない」「収穫できる等級(サイズ)が上がった」といった声も聞かれます。例えば九州のあるトマト農家では、ファインバブル装置を導入後に収穫量が例年比110%(1.1倍)に増加し、実がひと回り大きく揃うようになったとの報告があります。また別の事例では、露地栽培のズッキーニやニンニクで従来の1.3倍の大きさまで生育した例、霜害で一度しおれたレタスがファインバブル潅水で復活した例、ダイコン・ニンジンの圃場で病気発生が軽減した例など、各地で様々な成果が報告されています*4。
重要なのは、こうした効果はあくまで「水や栄養の与え方を工夫した結果」として現れるものであり、従来の栽培管理の代替というより補助的な技術だという点です。農研機構など公的研究機関でも検証が進められていますが、土壌条件や栽培方法によっては効果が出にくい場合もあります。そのため、導入の際はメーカーや専門家の指導のもと、自分の作物・環境で試験を行って効果を確認しながら使うことが推奨されています*5。いずれにせよ、日本各地の事例を見る限りでは「うまくハマれば増収・品質向上が見込める新技術」として、農家にとって魅力的なソリューションになり得ると言えるでしょう。
海外の導入事例
ファインバブル技術(海外では主に「ナノバブル」と呼ばれます)は、日本だけでなく世界の農業分野でも徐々に注目されています。欧米やアジアでも、水不足対策や環境負荷低減の観点からナノバブル灌漑の研究・導入が進んでいます。
例えばフィンランドでは、大学と企業が協力してナノバブル灌漑技術の実証プロジェクトを行い、トンネル栽培のイチゴで収量が15.5%増加したとの報告があります6。また「灌水水中の酸素濃度を高めることで植物の免疫力が向上し、殺菌剤・農薬の使用削減につながった」という知見も得られています6。実際、このプロジェクトに参加したフィンランドの複数の園芸農家では、ナノバブル装置の導入により根腐れ病(ピシウム病)などが発生しなくなり、収穫量が安定したという声が上がっています*6。ヨーロッパでは農薬削減や持続可能な農業が強く求められている背景もあり、ナノバブル技術は化学薬品に頼らない生産性向上策として期待されているようです。
アメリカでも、ナノバブル技術のスタートアップ企業が農業分野に参入しています。米国のあるメーカーは温室トマト栽培での導入実験を行い、トマトとキュウリの収量が向上し水利用効率も上がったというデータを公表しています。また別の報告では、水田でナノバブル水を用いて灌漑することでイネの収量が約8%増加したとの学術論文もあります。これらはいずれも単年・限定条件での結果ではありますが、海外においても概ね「10~20%程度の増収効果」が確認されつつあり、さらに酸素供給による病害低減など付加的メリットも評価されています*6。
海外のメーカーとしては、例えば**Moleaer社(米国)が農業用ナノバブル発生装置を商業展開しており、世界各地の農場やゴルフ場の池(水質改善)などに数百台規模で導入されています。またEOD社(フィンランド)**は先述のプロジェクトに参加し、自社の灌漑用ナノバブル装置を欧州の温室農家向けに提供し始めています。これら海外企業も「より少ない水や化学物質で収量アップ」「持続可能な農業への貢献」をキーワードに技術普及を図っており、日本発の技術がグローバルにも広がりつつある状況です。
代表的な製品・メーカー紹介
最後に、農業用ファインバブル装置の主な製品例と、それらを手掛けるメーカーについて紹介します。日本ではファインバブル産業会の活動もあって、多くのメーカーがこの技術に参入しています。その中でも農業分野で実績のある主な企業・製品は次の通りです。
- 丸山製作所(長野県) – 農業機械大手の丸山製作所は、農業用ウルトラファインバブル発生装置「MUFBウルトラポンプ」シリーズを展開しています4。バッテリー式やエンジン式など用途に応じたモデルがあり、灌水ホースや潅水タンクに接続して使うことで簡単にファインバブル水を作れます。丸山製作所のホームページでは水稲苗や葉物野菜、果菜類など多数の導入成功事例が紹介されており、「欠株がなくなった」「収穫量が○割増えた」など具体的な効果報告が載っています4。農家にとって馴染み深いメーカーだけに、アフターサービスや使い方のサポートも手厚いのが魅力です。
- ワイビーエム(YBM, 福岡県) – 元々水処理装置などを手掛けてきたメーカーで、ファインバブル技術の黎明期から関わっています。YBMはキャビテーション(液体の渦による減圧沸騰)を応用した独自の発生方式を持ち、産業用の**「フォームジェット」や小型高効率の「ファビー」**といったファインバブル発生装置を開発しています7。特にフォームジェットは大容量の水処理向けで、農業では大規模水耕施設の養液循環や養魚場の水質改善などに使われています。YBMはファインバブル産業会の創立メンバーでもあり、技術的な情報発信(例えばファインバブルのWebマガジン運営5)にも積極的です。
- OKエンジニアリング(東京都) – 中小ながらユニークな「OKノズル」という製品を製造する企業です。OKノズルは配管に取り付けるだけでマイクロ・ウルトラファインバブルを発生させる特殊ノズルで、農業用には灌水パイプラインに組み込んで利用されています。実績として、熊本県のミニトマト農家で収穫量46%増などの成果が公表されており*7、高い効果が得られた事例もあります。製品ラインナップも豊富で、温室の循環装置向け大流量タイプから小規模菜園向けまで取り揃えているのが特徴です。
- その他のメーカー – 上記のほか、産業機器メーカーのIDEC株式会社(大阪)もウルトラファインバブルの研究開発に早くから取り組み、2012年には世界で初めてウルトラファインバブルの存在証明を学会発表したことで知られます。現在は産業用水処理向け装置などを手掛けています。また株式会社Ligaric(福岡)は、西日本高速道路会社と協業してファインバブル洗浄装置「BUVITT」を開発し、農業分野にも応用を広げています。家庭向けではMTG社(愛知)の「ウルトラファインバブル発生シャワーヘッド」など美容・衛生用途が人気ですが、農業資材メーカーでも散水ノズル型やポンプ型のファインバブル装置がいくつか市販されています。海外メーカーでは先述のMoleaer社やEOD社の他、中国や韓国でも農業用ナノバブル装置が登場し始めています。
これからファインバブル装置の導入を検討する際は、自身の栽培規模や目的に合ったタイプを選ぶことが大切です。小さなビニールハウスで試したいなら安価なノズル式や小型ポンプ式、大規模施設園芸なら循環タンク対応の本格装置、といった具合に様々な選択肢があります。装置の価格帯は性能や規模によって幅がありますが、小規模向け簡易タイプなら数十万円程度、大規模施設向け高性能タイプでは100万円以上するものもあります(メーカーごとの価格目安を確認してください)。導入コストに見合う効果が得られるかどうか、補助金の活用も含め検討すると良いでしょう。
おわりに
ファインバブル技術を農業に応用した装置は、「目に見えない泡」の力で作物の生長を支える新しいアプローチです。科学的な裏付けも少しずつ明らかになりつつあり、先進的な農家や企業によって現場での有効性も報告されてきました。従来の肥料や農薬に置き換わるものではありませんが、水と空気という基本資源を賢く利用して作物のポテンシャルを引き出す補助手段として、ファインバブルは大きな可能性を秘めています。
農家向けの自然な語り口で説明してきましたが、いかがでしょうか。もし興味が湧いた方は、ぜひ身近なところでファインバブルを体験してみてください。例えば、家庭用のお風呂グッズでウルトラファインバブルのシャワーヘッドを試してみると、その洗浄力や保温効果などを実感できるかもしれません。それと同じ技術が農業にも活かせると思うと、なんだかワクワクしますね。
今後さらに研究が進めば、ファインバブル装置は農業にとって欠かせないツールの一つになるかもしれません。環境に優しく、作物にも人にもメリットがあるこの技術を上手に取り入れて、より良い農業経営につなげていきましょう。
*1 一般社団法人ファインバブル産業会「ファインバブルとは? ~定義・特徴~」https://www.fbia.or.jp/about/whatsfb.html
*2 スタディラボ「日本発【ファインバブル】の研究!物流、農業や医療まで多くの用途で広がる『泡』の活用。」https://studyu.jp/feature/theme/finebubble/
*3 ファインバブル産業会「植物成長促進(ファインバブルの効果と原理)」https://www.fbia.or.jp/fine-bubble/fine-bubble-effect-and-principle/growth/plants/
*4 丸山製作所「ウルトラファインバブル 農業への活用」https://maruyama-ufb.jp/agriculture/
*5 経済産業省 九州経済産業局「ファインバブル活用事例集」(2018年)https://k-rip.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/finebubble_ver4.pdf
*6 Hortidaily “High expectations for nanobubble technology in agriculture” (2023年9月19日) https://www.hortidaily.com/article/9643729/high-expectations-for-nanobubble-technology-in-agriculture/
*7 有限会社OKエンジニアリング「農業分野 – マイクロバブル・ファインバブル発生OKノズル」https://ok-nozzle.com/use/agriculture/