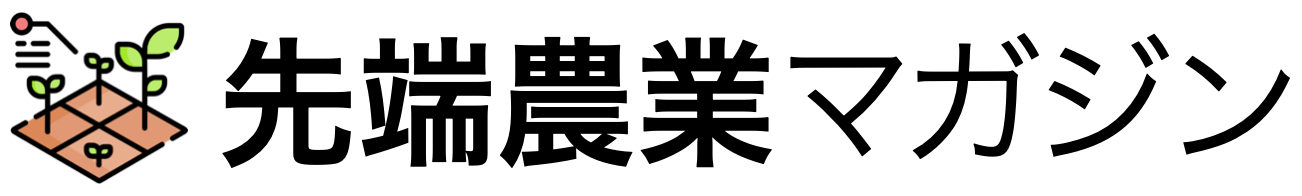「企業は、農業に参入しやすいの?」
「新しい事業として農業に参入したいけど、どのようなメリットがあるのかわからない」
「企業がどのように農業に参入すれば良いのか知りたい」
このように考えていませんか?新規事業として農業参入に興味があっても、知見がないと始めづらいですよね。
結論として、企業の農業参入は増加傾向にあり、さまざまなメリットがあります。
本記事では、企業の農業参入の現状やメリット・デメリットを解説します。農業参入の企業事例や参入する流れまで説明しますので、新規事業にチャレンジする参考にしてみてください。
企業の農業参入についての理解を深めて、失敗しない事業につなげましょう。
お問い合わせはこちら
【増加傾向】企業の農業参入の現状

昨今、農業分野における企業の進出が進んでいます。実際に、農林水産省によると、令和4年1月1日時点で、全国で4,202の法人が新たに農業に参入しています。
また、平成22年から令和4年にかけて、毎年平均334の法人が農業に新規参入しているため、拡大傾向にあると言えるでしょう。
以前までは、企業の農業参入はしづらい状況でした。しかし、平成21年12月の農地法改正により、農業生産法人に限らず、一定の条件を満たせば、一般法人でも農地を貸借し全国どこでも農業に参入できるようになっています。新規参入の規制が以下のように大幅に緩和され、参入しやすくなっているのです。
- 農地のすべてを効率的に利用すること
- 周辺の農地利用に支障がないこと
また、有機農業(化学的に合成された肥料・農薬を使わずに、環境負荷を低減する農業)に着目すると、平成22年の1,730人から平成28年には3,440人へと、参入者が倍増しているのがわかります。
有機農業について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
【最新版】有機農業参入の現状!メリット・デメリットをわかりやすく解説
企業が農業に参入する2つのメリット

企業が農業に参入するメリットは、以下の2点です。
- 既存の事業や技術とのシナジー効果を期待できる
- 企業の農業参入を支援している国や自治体が多い
1.既存の事業や技術とのシナジー効果を期待できる
企業は既存の事業や技術と農業を組み合わせることにより、相乗効果を享受できます。
例えば、自社のIT技術を活かして、農作物の生産を管理し、収穫時期を予測するようなツールを開発する方法が挙げられます。
また、不動産業界での経験を活かして適切な農地を探し出す方法も考えられるでしょう。
このように、異なる分野の知識を農業に応用すると、生産性アップや質の高い作物の栽培につながります。
2.企業の農業参入を支援している国や自治体が多い
企業が農業に新規参入する際には、国や自治体からの支援を受けやすいのがメリットです。
具体的には、国は、農業の現場で活躍する企業に対して、補助金などの支援を行っています。
そのほかにも、農林水産省では「農業をはじめる.JP」というWebサイトを運営し、農業に関する知識や情報を提供しています。例えば、就農希望者を雇用する際の助成金や検定などの情報が記載されています。
農業に参入する際や継続して事業を展開するときに役立つでしょう。
企業が農業に参入する2つのデメリット

メリットの多い企業の農業参入ですが、以下2点のデメリットもあります。
- 安定生産の仕組みづくりが難しい
- 人的・金銭的コストがかかる
1.安定生産の仕組みづくりが難しい
農業は、良質な作物を安定かつ大量に生産する体制構築が難しい傾向にあります。知識や経験の不足だけでなく、天候や土壌の状況など、自然環境の変動に大きく影響されるからです。
したがって、農業に参入するときは「どの作物を栽培するか」「どのような戦略を立てるか」を事前に計画する点が求められます。
後述する「【6Step】企業が農業に参入する流れ」で、農業に参入する際の戦略を解説するため、参考にしてみてください。
2.人的・金銭的コストがかかる
農業への参入には、人的・金銭的コストがかかるのがデメリットです。
特に、これまで農業経験がない企業が参入する場合、効率的な生産を実現するために、スマート農業(ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業)を行うことが望ましいでしょう。
しかし、スマート農業には初期投資が必要となるため、財政的に余裕のある大企業でなければ参入が難しい傾向にあります。
さらに、新たに農業法人を設立し、従業員を雇用する場合には、社会保険への加入が必要となる場合もあります。これにより、人件費だけでなく、社会保障費用も含めた総コストがかかるため、企業にとっては負担が大きくなる可能性があるでしょう。
このような理由により、農業に参入する際には、人員やコストの確保も考慮することを推奨します。
企業の農業参入の成功事例2選

本項では、大企業における農業参入の成功事例を紹介します。
- イオンアグリ創造株式会社
- 株式会社ローソン
1.イオンアグリ創造株式会社
イオングループであるイオンアグリ創造株式会社は2009年に設立され、若者を積極的に雇用し、地域農業の近代化を目指しています。
参入した地域である大分県は、土壌が阿蘇山の火山灰土で水はけは良いものの、栄養分が流出しやすい課題がありました。それにより、アブラナ科の作物においては連作障害(同じ場所で長年栽培し、生育が悪化したり枯れたりすること)が起こりやすくなっています。
しかし、この土壌が白ねぎの栽培には適しており、水はけの良さが逆に梅雨時の雨量に対応できる有利な条件となりました。それにより、白ネギを安定的に収穫できるようになっています。
また、収穫された白ねぎは、イオングループ全体に供給され、九州内にあるイオンやマックスバリュ、近畿や中部地方の一部の店舗にも出荷されています。
地形を活かしながら、自社が保有する販売網を最大限に活用している点が成功したポイントです。
2.株式会社ローソン
株式会社ローソンは、ローソンファームを通じて、グループ店舗に対する安全かつ安心な野菜の持続的な供給を目指しています。ほかにも、次世代の若い農業者を支援し、育成する目標も掲げました。
具体的には、生産者が主導となって近隣の農地を借り入れたり、提携を結んだりすることにより、野菜の安定供給を実現しています。
特に、各産地における若手の生産者との提携に重点を置き、長期にわたって継続可能な野菜の供給体制を築いている点が特徴です。
これにより、地域農業の活性化にも貢献し、企業としての社会的な責任を果たしながら、農業参入を成功させています。
企業の農業参入において失敗しないためのポイント

企業が農業に参入する際に失敗を避けるためには、以下の2点を抑えておきましょう。
- 入念な準備を行う
- 運転資金を準備する
農業への参入時には、農地の確保や土壌改良を進める必要があるため、事業を開始するための準備を進めておきましょう。また、将来的な販路の確保や必要な知識や技術の習得、労働力の確保といったさまざまな準備も求められます。
このような準備により、農業に参入する際には、参入までに平均約20.2か月の準備期間が必要です。
そのほか、農業は短期間で利益を生み出すのが難しいため、十分な運転資金を確保してください。利益が出るまでの期間は事業を継続できるように、資金計画は慎重に行うことが望ましいでしょう。
【6Step】企業が農業に参入する流れ

本項では、企業が農業に参入する流れを6ステップで解説します。
- 事業計画の立案
- 参入する地域・農地の選定
- 資金の確保
- 施設の準備
- 雇用の確保
- 農業への参入
1.事業計画の立案
企業として、どのような目標や計画をもって農業に参入するのかを明確にし「どの作物を育てて、収穫した農産物をどの市場で販売するのか」を考える必要があります。
目的ごとに検討するべき材料は異なりますが、イニシャルコストやランニングコストを基にして計画を進めることが必要です。
イニシャルコストでは、ビニールハウスの仕様や内部設備などを検討します。
一方で、ランニングコストでは、年間の売上原価や販売費、一般管理費を見積もりながら必要な人員やコストを把握します。特に大規模な農業経営を目指す際は、作業時間に基づいて人員の確保をしましょう。
また、作物の選択と事業計画においては、収支シミュレーションが有効です。収支シミュレーションが可能なWebサイトがあるため、ツールを活用して計画を立てましょう。
2.参入する地域・農地の選定
企業が農業分野に挑戦する際には「参入する地域・農地の選定」を行う必要があります。
農地の選定に関しては、土地の条件を明確にしたうえで、各自治体や農業委員会と相談を重ね、適切な候補地を探し出すことから始めます。その際には、以下のような多角的な観点から、検討しましょう。
- 土地が企業が描く目標や意図に適しているか
- 栽培に向いているか
加えて、水質の調査をはじめとしたリスクの事前把握と対策の立案も重要です。
また、農業活動が周囲の環境に影響を与えないように、慎重なチェックが求められます。
特に、化学肥料や農薬の使用については、過剰な散布を避けることで、環境への配慮を忘れない姿勢が重要です。
3.資金の確保
企業が農業に参入するときは、長期的に挑戦し続けられるように資金の確保を行いましょう。
農業経営を始めるには、農地を取得するための資金はもちろん、栽培施設の設置や作業用の車両など、さまざまな設備の準備に費用がかかります。
特に、大規模に農業を営む計画の場合、多くの労働力を確保するためにも、十分な資金の用意が重要です。
4.施設の準備
農業施設には、栽培エリアだけでなく、機器を配置するスペースや収穫物を選別するエリア、出荷のためのスペースも必要です。
それに加えて、日々の運営を管理するための事務所や、施設全体をコントロールする制御室の設置も欠かせません。
これらの施設の整備は、農業事業の効率化と品質保持に直結するため、細部にわたる配慮が求められます。
5.雇用の確保
農業に参入する際には、作業を行う人員の確保が重要です。事業の規模を計算したうえで、どのくらいの人数が必要なのかを計算しておきましょう。
その際には、就農を希望する人々を雇用する農業法人に対して交付される「雇用就農資金」が利用できる場合があるため、活用してみましょう。
6.農業への参入
必要な準備を整えたら、企業は農業に参入できますが、計画が予定どおりに進むわけではありません。
実際に作業を進めながら、さまざまな課題が浮かび上がる場合もあるでしょう。そのため、柔軟に計画を見直し、修正を加える点が重要です。
農業に参入しながら、売上・利益やかかるコスト、収穫量などのデータを見て、改善していきましょう。
企業の農業参入ならトクイテンへお問い合わせください

昨今、農地法の改正などにより、これまで参入できなかった企業が農業に参入しています。
企業の農業参入は、既存の事業とのシナジー効果が期待できたり、国や自治体が支援していたりするメリットがあります。特に、多角的な業界に知見のある大企業は、既存事業の知識や技術を活かしやすいのが利点です。
一方で、企業の農業参入には、人的コストがかかるデメリットもあります。そのため、IT技術を活用した農業の自動化がおすすめです。
トクイテンは、有機農業の自動化を実現する「トクイテンパッケージ」を提供しています。トクイテンパッケージは、センサーを用いた作物のモニタリング・換気を行ったり、AI技術を活用したロボットを用いたりして、農作業の自動化を進めます。
「農業に参入したいけど、どのように進めれば良いかわからない」という方は、トクイテンに気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
参考サイト
・リース法人の農業参入の動向|農林水産省
・法人が農業に参入する場合の要件|農林水産省
・企業の農業参入について|千葉県
・企業の農業参入事例|大分県